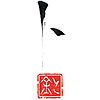鎮守

黄昏にて
少し昔。
夕暮れ時、闇が子供を追いかけていた。
街に夕焼け小焼けのメロディが流れ、
夕刊配達のエンジン音が消えるころ、
遊んでいた童たちが、公園から一人、二人、三人、
五人と去っていく。
それらすべては闇への恐怖と紐づけされ、
幼少期の私に至っては、明日の黄昏にすら心が怯えた。
鎮守の森が夕陽を背負い、
深く深い色味のシルエットに変わるとき、
心の余白も闇色に染まっていった。
そして現代。
人々は、それらの闇と接する機会を失いつつある。
恐怖を感じることも心の余裕の一部だったのだろうか。
人々は持て余すほどの彩を抱えながら、
手放した余白を探し、日々を彷徨っている。